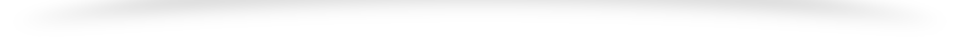「花衣(かえ)、こっちみたいだよ。」
そう言って彼女は右手を振りかざし、早くこっちに来るよう私をうながすのだ。その屈託のない笑顔に – 彼女は夢中になると子供のようなはじけた笑顔になるのだ – 私は引きつった笑顔でそれに答える。その笑顔の意味するところが伝わったのだろう、彼女は私のもとに戻ってきてくれたりすることは残念ながらなく、にっこりと微笑んでさらにさっさと前へと歩き始めた。どうやら私の笑顔は「後で追いつくから、先に行って欲しい」と理解されたようだ。やれやれ、彼女らしい反応であるが、それより今わたしが直面している問題は、なぜ私は彼女とここで山歩きをしているのか、という事だろう。私の住んでいる街はもともと平野部が少なく、県全体の平野部の占める割合がアマゾン並みに少ないのだ。だから街内に里山がどーんと鎮座してたりする。それ自体は小さい頃から見慣れている風景だし、ちょっとした遠足などでお世話になった記憶もあるのだから別にどうという訳ではないのだけど、今この里山にカフェが存在していることがそもそもの事の発端なのだ。まあったく、再度繰り返しになるけど、なぜ私はここで彼女の山歩きにつきあわなくてはいけないのだろうか?
彼女の名前は朝倉夕夏(あさくらゆうか)。
実は、それ以上の詳しいことについて正直わたしは知らないままなのだ。例えば、どんな家族構成でどこの出身で今どこに住んでいて何が趣味なのかも知らない。ケータイの番号も知らなければアドレスも知らない。その事について彼女が話すこともないし、私から問いかけたこともない。おそらく – 考えたくはないけれど – 彼女が事故にあって入院するようなことがあったとしてもお見舞いに行くどころかそれすら気づかない私がいるんじゃないだろうかと想像してしまう。なぜなんだろう? それすら今まで考えようとしなかった私がいた。あえてその理由を言えと言われたなら、私と彼女は大学受験に通う予備校でたまたま教室が一緒になっただけの間柄でしかないから、としか言いようがない。予備校というのはそういう人間関係の空間でしかないと思っていたからかもしれない。

「花衣、この山頂の公園にカフェがあるんだよ。」
肩で息をしている私に気づいているのかいないのか・・・。彼女は楽しくって仕方がないような明るい声で話しかけてくる。
「・・・・ねえ、夕夏。・・・・ちょっと聞いてもいい? ・・・この公園の入り口前にはバス停があるよね。どうして、、、いえ、バスの方が早くこれたんじゃないかと思うんだけど?」
「この山はね、」
そういって彼女はちょっと遠くを観ているような目で私をみながらしゃべり始めた。
「信仰対象となっている霊場のお寺があるんだ。全国からこのお寺を歩いて訪ねてくる人がずーっと昔からいたんだよ。せっかく近くに住んでいるんだもの、同じ路を歩いて登ってみたいじゃない。」 彼女が高校生の時に県外から引っ越してきたことは何となく知ってはいた。この予備校に通っているのも慣れない環境の変化で受験に失敗してしまったからだと- 本当かどうかは知らないけど – 噂話を耳にしたことがあるから。その彼女が地元の私でも知らないような事をなぜ知っているのだろう? ひょっとして私が知らなさすぎるのかな? 身近すぎて興味がなさすぎたかな?
「とにかく後少しで目的のカフェだよ、早く行こうよ。市内を一望できるらしいよ。」
えーっ、まだ、歩くの?と思った瞬間、視界を何かが横切った。思わず目で追いかけてしまう。あ、猫だ。そう思った瞬間、お互いの視線があってしまった。瞬間 猫は少し身を縮めたかと思うとスッと走り出してしまう。そのあっという間の動きを追いかけた私の視界には、猫に変わって白い建物が飛び込んできた。それはいかにも観光地の展望台でござい、という感じの3階立の白い建物だった。え? ひょっとして、あのいかにもって感じの所? 目的のカフェって? その建物に向って道案内をするかのように走りだしたさっきの猫の後ろ姿が視界に入った。
スタッフが日々感じた事などをつづっています。