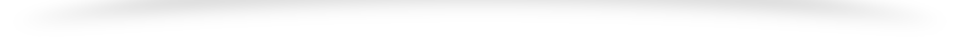「でも、よくこんな所、知ってるのね?」
「本当いうと、偶然なんだ、ここを知ったのは。」
そういうと夕夏(ゆうか)はハミングし始めた。それは私でも知っているアーティストの代表曲で、たしか何年か前の夏の甲子園の行進曲にもなったことのある曲だった。そして我が県出身のアーティストでもあるのだ。
「彼女の曲のなかでここでの思い出を書いた歌があるらしいの。どの曲かまでは知らないけどね。昔はロープウェイがあって、下にある川をまたいで山頂から対岸までロープウエイが引かれていたんだって? あー、私も乗ってみたかったなあー。ひょっとして花衣(かえ)は知ってる?」
一体いつの頃の話なのよ?って言って笑ったけど、なんでこの人はそんな事まで知ってるんだ?
お待たせいたしましたと言って店員さんが注文した品をトレーにのせて持って来てくれた。反射的に見上げた店員さんの顔を私はついまじまじと見入ってしまった。30歳後半くらいだろうか、化粧っけなしでほっそりとしたおとがい。長い腕と細い指が注文した品をテーブルに並べていくのを目で追ってしまう。
「・・・ 花衣ったら、目がハートになってるよ。」
夕夏は注文したカプチーノをアチッていいながら、ああいうタイプが好みなの? とちょっかいをだしてくる。うるさいなー、あなたは案外猫舌なのね、と私は砂糖もクリームもいれずにコーヒーを飲もうとする。
「なんていうか・・・、私って背が低いから、すらっとした人に憧れがあるのかな?」
「花衣だってじゅうぶん細いじゃない。」ありがとう、と言いながらも首は自然と横に振っていた。そうじゃないのよね・・・。そうかなーっていいながら夕夏は一緒に頼んだチーズケーキにフォークをいれる。一口ほおばって、うん、とうなずいて、花衣も一口どう?と言ってくれる。ひょっとしてかなりの甘党だったりするのかなと思いながら、実はあまり甘いモノが好きでない私はニッコリ微笑んでコーヒーを口にして話をそらした。
なんか今ごく普通に話をしているだけなのに、店内にいる人の視線が私達に集中しているのが分かる。もちろんその視線の先にあるのは私ではなく彼女になのだが、どうにも注目されることに慣れない私はしだいにうまく呼吸ができなくなってきて意識的に呼吸を整えようとする。少なくてもダメだし多ければいいというものでもないから。ほんと、めまいがしてきそうだった。当の本人はどこ吹く風でチーズケーキをパクパクと食べている。夕夏らしいなと思ったし、またそれが絵になるのよね、この人は。
・・・そもそも彼女はなんで私とここにいるんだろう? 自意識過剰みたいに聞こえると嫌だからあまり考えたくないのだけど、私の何がよくて彼女は私といっしょにいるんだろう?
「ひとりはさみしくないの?」
たぶん彼女はそう言ったんじゃないかと思ったけど、急にぼそりと言ったのでほんとに私は聞き取れなかった。
「えっ? ごめんなさい、なんか言った?」
なんでもない、っていって彼女は残りのチーズケーキをほおばった。私もそれ以上その事について追いかけることもせず、うっすら冷たくなったコーヒーをすすった。コーヒーはよく飲むわりにはここのコーヒーが美味しいのかどうか私にはわからなかった。少なくともインスタントじゃないなとは思ったけど。そもそも私はコーヒーという液体が美味しいものだと思って今まで飲んでいなかったのかもしれないな、ほんとはなんでもよかったのかな、なんてふと考えてしまった。
「さてと、そろそろ行きましょうか。もうすぐバスがくる時間だよ。」
「え? 帰りはバスにするの?」
「実はあたしも歩いて降りるのはしんどいかなあー、って思って一応調べておいたんだ。」
「ふーん、あと何分ぐらいでバスがくるの?」
「んーっと、15分ぐらいかな?」
「じゃあ、公園内をちょっと散歩してからバス停に行きましょうか。」
夕夏はくしゃって笑って「さっき道案内してくれた猫にあいさつできるかもね」と言ってトレーを片手に席を立った。私も両手でトレーを持ち上げて彼女の後を追いかける。なぜだろう? いま私はいい笑顔になってる気がする。彼女といると私は笑顔になれる、今日はいい日になりそうだ、と思った。
スタッフが日々感じた事などをつづっています。