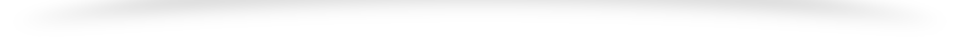ハートというモノが存在するとすれば、この位置なのだろう。
まづ、理不尽だといっていい程の不安感が私の胸部を握りしめる。そこは心臓でもなければ胃でもない、もっと表層のところにある何かだ。そこで起こる痛みがいつも私を不安にさせるのだ。ここが痛みだすと、もうひたすら我慢するしかない。ハートってもっと素敵なことに使うことになってるはずなんだけどな、なんて思う。夕夏がいなくなっただけでどうしてこんなにも不安になるのだろう? でも時間さえたてば落ち着くのは間違いないのだからじっと耐えるしかない。ただ今回は私の身体はそれだけでは終わりにしてくれなかった。次に、心臓がその存在を確認できるぐらいに私のなかで暴れはじめたのだ。なぜ?どうして? と思いながらも、とにかく深呼吸して対処してみる。こういう場合は、息を吐くことに集中しながら呼吸するといいのだ。そのおかげだろうか、少しは収まったように思うけど、まだ心臓がぐずっているのが分かる。まずい、な。不安感もまだ治まらない。私の身体が私を拒否しているかのよう。でもだから私にどうしろというの? ちくしょう、気分がひどく悪くなる。吐くものはないとわかっていても、吐けばひょっとしてスッキリするかもしれないなと考えてしまう。自然と身体が二つ折りに曲がっていくのと同時に全身も硬直していくのを感じる。とにかく呼吸を整えるんだと意識をそちらに集中する。ほんとに・・・めまいがしてきた。心臓から血液が回ってこなくて全身が冷たくなる感覚に襲われる一方で全身から汗が吹き出してきたのが分かる。暑いからなのか冷や汗なのかどうかも今は判断できない。これは・・・倒れるしかないかな、と思う。でもこのイス、ちょっと汚れてるのよね。横になっちゃうと髪も服も洗わなきゃだな、めんどくさいなあ、なんてどうでもいいことを我ながら考えてしまう。それどころじゃないでしょ、って自分につっこんでみたりする。
夕夏の姿が視界に入ったのと私が椅子に横たわったのはほぼ同じタイミングではなかっただろうか。視界の隅から真剣な顔をして彼女が走りよってくる姿が私の目の網膜に写っていた。
「ちょっ、、、花衣、どうしたの? 気分悪いの?」
ひたいに手を当ててくれる。「手当て」とはよく言ったものだなと思う。そのほんのりと温かい手のひらを起点に、私を拒否していた私の身体が少しづつ落ち着きを取り戻していく感じがする。そして少しづつ私の意志が身体に届くようになっていくのが分かる。それになにより私が気持ちいい。ずっとこのまま手をはなさないでと真剣に考えてしまう。あ、うそうそ! なにバカな事考えてるの!
でも、あれ? 誰? 気がつくと夕夏の後ろに知らないおばあちゃんが立ってこちらを見ているのに気づいた。えーっと、たぶん知らない人だよね。夕夏が驚いてるのを見かけてきてくれたのかな?
「あー、これは”ひがはいった”がやないろうか。お兄いさん。」
「え? ひが・・・なに?」
「まだ5月やけど、もうお日いさんは強いきね。ほら、あんたが持っちゅうやつを貸してみいや。」
そういって夕夏の持っていたペットボトルを受け取ると、- おばあちゃんも青空市で買い物をしてきたのかな? – 買物袋から取りだしたタオルでそれをぐるりと巻いて、どっこいしょって言いながら私のひたいにそれを当ててくれた。ひんやりとした存在がひたいを通して感じられた瞬間、私は思わずため息をもらしてしまった。よかった、いつも通りの私の身体だ、と。そして全身から緊張がとけ、筋肉がほぐれていくのが分かる。その空気は彼女達にも伝わったのだろう、夕夏は大きくため息をついた。ごめんなさい、心配をかけてしまって。自分の手のひらを開いて見てみる。ずっと握りしめていたのだろう、爪がくいこんだあとが残っていた。そしてせき止められていた血が流れ始めたのだろう、いつも以上に手のひらが紅くなっていた。
・・・もう大丈夫だ、と私は思った。胸の痛みも治まったようだ。
だからかもしれない。夕夏とおばあちゃんに囲まれて、ひょっとして私は一人ではないのかもしれないとも思った。
スタッフが日々感じた事などをつづっています。